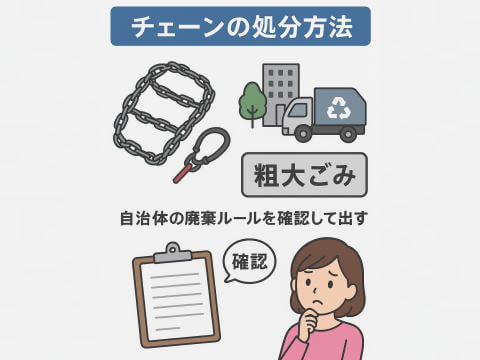
タイヤチェーンを使わなくなる、使えなくなる理由としては、クルマの買い替えによってサイズが合わなくなる場合が多く、更に摩耗や劣化が進んで安全に使用出来ない状態に至ることが挙げられます。
非金属チェーンは特に摩耗が早く、本体が削れたり亀裂が出たりしやすく、金属チェーンは比較的耐久性が高いものの、それでも錆や伸びなどの劣化は避けられません。そして、見た目に問題がなくても製造から5年以上経過した製品は素材そのものが経年で硬化したり柔軟性を失ったりする為に、本来の性能を発揮出来なくなっていきます。
この5年という耐久目安は感覚的なものではなく、JASAAの認定品に付属する警告書でも明確に示されている基準です。非金属チェーンやケーブル式チェーンは5年間継続使用すると劣化により性能が低下する可能性があり、たとえ全く使っていなかった場合でも素材の経年変化によって安全性に懸念が生じるとされています。
つまり、「見た目が新品同様」でも「未使用品」でも、5年以上経過した時点で本来の強度や柔軟性が保証されなくなるということです。
その為、使わなくなったチェーンを保管だけしておくことはあまり意味がなく、むしろイザという時に装着したら破損してクルマを傷つけたり、走行中に外れて事故に繋がったりする危険があります。
こうした背景から、不要になったチェーンは適切に廃棄することが推奨されますが、問題となるのが自治体ごとのゴミ区分の違いです。
例えば神奈川県横浜市は、プラスチック製なら縦横高さ全てが50cm未満であれば「燃えるゴミ」、縦横高さ全てが50cm以上であれば「粗大ゴミ」。金属製は縦横高さ全てが30cm未満であれば「小さな金属類」、縦横高さ全てが30cm以上であれば「粗大ごみ」となっています。
埼玉県川口市は、ゴム製なら「粗大ゴミ」、金属製なら40cm以内は「資源物 金属類」、40cmを超えるものは「粗大ゴミ」です。
自治体によって素材や大きさの基準がまったく異なり、同じチェーンでも扱いが変わるので、必ず自分の住んでいる地域のルールを確認する必要があります。

またこうした処分の煩わしさから、使わなくなったチェーンをオークションに出してしまおうと考える人もいます。
しかし、ここでも前述の5年ルールが大きな問題になります。製造から5年以上経過したチェーンを出品すれば、外見が良くても素材の劣化が進んでいる可能性が高く、買った人が使用した際に破損や事故が起きることがあります。
出品者の説明不足や認識不足が原因でトラブルに発展すれば、法的な責任を問われる可能性も否定出来ません。逆に購入する立場でも、見た目だけでは製造時期や劣化の進行度が分からないので、非常にリスクが高い買い物になります。
こうした事情を総合的に考えると、チェーンは使わなくなった時点で廃棄し、必要であれば新品を購入するという選択が最も安全で確実です。雪道走行はクルマの操作性と安全性が大きく左右される領域であり、チェーンは緊急時に命を守る道具でもあります。
だからこそ信頼出来る状態のものを使い、劣化や製造年を気にしながら中古品をやり取りするより、新品を選ぶ方が結果的に安心に繋がります。
